当クリニックは、日本小児科学会専門医による診療を行っております。
小児科では、子どもの病気全般を診療します。
● 一般診療(【午前】9時~12時、【午後】16時~17時30分)は予約制ではありません。直接ご来院ください。
15時~16時は予防接種のみの外来となりますので、ご注意ください。
(予防接種に来られた方が、感染症の患者さんと接触しないようにするために時間を分けています。ご了承ください。)
● 症状などによって、診察の順番が前後することもありますのでご了承ください。
● 当院ではできない検査・治療が必要と判断される場合、専門診察が必要と判断される場合、入院加療が必要と判断される場合は、近隣病院あるいは専門病院に紹介状を書きます。
● 登園許可、治癒証明、入園前の診断書、その他の診断書 も可能です。
※ 診断書は有料になりますが、ノートに記載する登園許可、治癒証明は無料です。
【 くすの木クリニックの診断書 】
| 複雑な診断書(自動車保険関係、役所に提出する詳細な診断書、英語の診断書など) | 5,200円 |
| 一般的な診断書(入園前診断書、入学前診断書、留学前の診断書など) | 3,100円 |
| 簡単な診断書(病名のみの診断書) | 1,000円 |
・登園許可、治癒証明のノート記載は無料です。ただし、症状が改善した時点で再診をしていただきます。保育園、幼稚園の手帳、学校の健康手帳を持ってきてください。
【 当院でできる小児処置 】 ↓知りたい項目をclick!!
【 当院でできる検査 】 ↓知りたい項目をclick!!
【 小児科でよく見る症状・相談 】 ↓知りたい項目をclick!!
【 当院でできる小児科処置 】
鼻吸引
- ・ 主に赤ちゃんが対象です。鼻が詰まって、うまくおっぱいを飲む事ができない時、眠っていても息が苦しそうな時などに鼻を吸ってあげると、一時的ですがとても楽そうになります。
(尚、市販の鼻吸引器でも、うまく使える場合はとても効果的です。ただ使いこなすのがなかなか難しい・・・。)
吸入
- ・ 喘息発作の時は気管支拡張薬の吸入を行います。
- ・クループの時は、アドレナリン(血管収縮薬)の吸入を行います。
浣腸
- ・ 便秘症の乳児にはまず浣腸をします。慢性便秘であれば、おうちでも浣腸をしてもらえるように、指導いたします。
- ・ 腹痛が続いている患者さんで、原因が分からない時も浣腸をしてみます。浣腸後の症状の変化、浣腸ででた便の性状などが、診断にも役に立ちます。
点滴
- ・ 胃腸炎や周期性嘔吐症で嘔吐が持続し、脱水・低血糖が懸念される時は点滴を行います。
- ・気管支喘息の中発作以上で、吸入で改善しない時はステロイド点滴の適応になります。
【 当院でできる検査 】
胸部レントゲン・腹部レントゲン
咳が続く場合に肺炎の評価をしたり、腹痛が持続する場合に、腸管ガスの分布を確認したりします。
超音波検査
心電図
迅速検査(インフルエンザ、RSウイルス、溶連菌、アデノウイルス)
綿棒で鼻咽頭粘膜、扁桃粘膜などを擦って、その場で診断できる検査です。
血液検査
炎症反応の評価、貧血の評価などは、院内で迅速検査ができるため、15分ほどで結果が分かります。それ以外の項目については、外注検査となります。
尿検査
尿定性検査(尿潜血、尿たんぱく、尿中白血球、尿糖など)は院内で可能です。
培養検査
弱視スクリーニング検査
網膜にきちんとピントが合っているかをみる検査です。
詳細はこちら>>
【 小児科でよく診る症状・相談 】
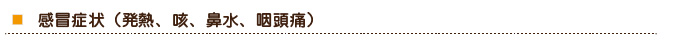
子どもの風邪
風邪(上気道のウイルス感染症)では、抗生剤の必要はなく対症療法で様子をみます。一番大切な事は、しっかり休み、ぐっすりと眠ることです。ただし、症状が悪化する時、痰がらみの咳が長引く時は、中耳炎、副鼻腔炎などの細菌感染症が合併したり、肺炎の可能性もありますので、経過に応じて検査や抗生剤を検討します。
子どもが変な咳をする
風邪の時に、クループと呼ばれる特殊な咳をすることがあります。これは、声門付近の粘膜がむくんで、おっとせいが鳴くような、こもった咳がでる状態です。成人ではほとんどみられませんが、小児ではよくあります。軽いクループであれば、そのまま様子をみますが、息を吸うのがつらそうで喘鳴が聞こえるような場合は、むくみをとる吸入や炎症を抑える点滴が必要です。入院が必要になることもあります。
子どもがすごく喉を痛がる
子どもがすごく喉を痛がって唾液も飲みこめないような時は、風邪ではなく急性喉頭蓋炎という怖い病気の可能性もありますので、すぐに受診しましょう。
夏かぜについて
いわゆる「夏かぜ」は、夏に流行するウイルス感染症です。咳、鼻水はあまり目立ちませんが、軟口蓋根部、前口蓋弓に水疱疹ができて、喉を痛がったり、身体に発疹ができたりします。
溶連菌扁桃炎
溶連菌扁桃炎(咳、鼻水がなく咽頭痛のみの事が多い)の場合は抗生剤治療が必要です。腎炎、リウマチ熱につながることもありますので迅速な検査が大切です。
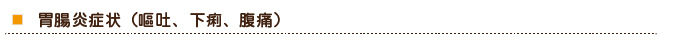
特に乳幼児は脱水・低血糖になりやすいので、注意が必要です。嘔吐・下痢が続き、水分摂取ができない場合は点滴を行います。細菌性胃腸炎(カンピロバクター、サルモネラなどの食中毒)の場合は、高熱、腹痛、血便など症状が強いので、学童児でも点滴や入院が必要になることがあります。
胃腸炎だと思っていても、腸重積(乳幼児)、虫垂炎(学童)などの病気である可能性もあります。
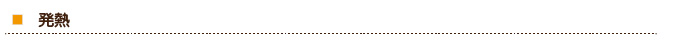
- ・ 発熱以外の症状や所見がなく、高熱のみが続く場合は、熱の原因を調べるための検査が必要です。
- ・ 生後3ヶ月未満(生後90日未満)の発熱は、重症感染症の判断が難しいため、血液検査を行います。
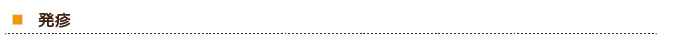
- 発疹には多種多様なものがあります。
- ①感染症に伴う発疹(麻疹、風疹、水痘、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、EBウイルス感染症、手足口病、突発性発疹、りんご病、、、など)
- ②皮膚感染症(とびひ、水いぼ、汗疹、、、など)
- ③その他(川崎病、紫斑病、帯状疱疹、、、など)
「発熱を伴っているか」「リンパ節が腫れているか」「水疱疹(水をもった発疹)か膿疹か丘疹か」「紅斑か紫斑か」「口腔内に発疹があるか」「身体のどの部位にできているか」「周囲の流行状況」などにより診断をします。
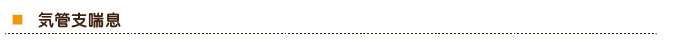
- ・ 喘息は気道の慢性のアレルギー性炎症と考えられています。まずは、喘息発作の回数を減らし、炎症を落ち着かせ、傷んだ気道粘膜の状態をよくする事。これが、次の発作の予防にもなります。
- ・ 喘息の治療には「①発作時の治療」と「②発作を起こさないようにするための治療」 があります。
- ① 発作時の治療は、まず現在の呼吸症状をよくすることが目的です。気管支を広げる薬の吸入、内服をします。それで改善がない場合は、ステロイドの点滴を行います。
- ② 発作を起こさないようにする治療では、ロイコトリエン受容体拮抗薬(好酸球の炎症を抑える薬)、吸入ステロイドが中心となります。
- ・ 喘息に関しては、「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン」が数年ごとに改訂されて出されています。治療はこれに沿って行うことになります。
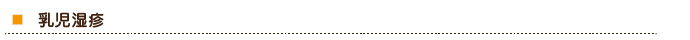
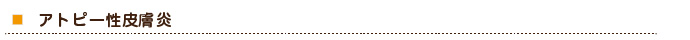
- ・ 治療の根本はスキンケアです。
- ① 石鹸を使って、汗、垢、黄色ブドウ球菌などのばい菌をしっかりと洗い流します。
- ② 入浴直後に保湿剤を使用します。
- ③ 赤みの強い部分には弱いステロイド軟膏を使用します。
- ・ 過剰に洗うことは皮膚によくありませんが、石鹸を使ってきちんと洗うと、塗り薬の効果が劇的によくなります。
- ・ スキンケアしているにも関わらず症状が改善しない場合は、食物アレルギーが関与している可能性もあります。
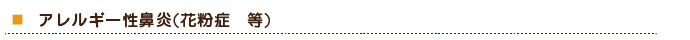
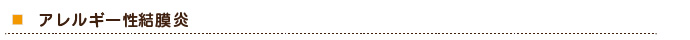
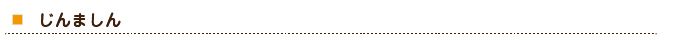
- ・ じんましんは、かゆみを伴う、地図状や円形の膨疹(膨らんだような発疹)です。場所を変えて出たり消えたりします。
- ・ 原因が分からないことも多いです。疲れているとでやすくなります。
- ・ 抗アレルギー薬の内服がよく効きます。
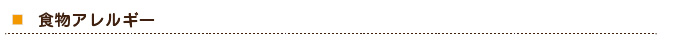
- ・ 特定の食べ物を摂取して直後に症状がでた、毎回同じ食べ物でじんましんが出るなど、はっきりとした病歴があれば、血液検査でアレルギー検査を行います。
- ・ アトピー性皮膚炎で、毎日きちんとスキンケア(石鹸できれいにあらってステロイド軟膏、保湿剤を使用)をしているにも関わらず改善がない場合は、食物アレルギーが関与していることがあるため、アレルギー検査を行います。ただし、 乳児湿疹というだけではアレルギー検査の対象にはなりません。
- ・ 乳児期に多い卵白アレルギーでは、年々耐性を獲得して学童期には普通に摂取することができるようになる事が多いので、年単位で評価をして、抗原性の低い食品の摂取を少量からトライしていきます。
- ・ 多数の食物にアレルギー反応がある場合、アレルギー症状が非常に強くでた場合、アレルギー検査の数値が異常に高い場合などは、専門病院を紹介します。
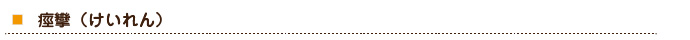
- ・ 小児期で一番多い痙攣は熱性けいれんです。
熱性けいれんは、こどもの脳がまだ発達段階で、発熱に対する感受性が高いためにおこるとされます。熱の上がりはじめ(発熱初日)に起こりやすいです。8%の人が子どものころに経験するといわれていますが、体質もあるようで、両親や兄弟に熱性けいれんの既往があると、熱性けいれんをおこしやすくなります。発症年齢は6か月~6歳で、小学校に入ると熱性けいれんはほとんどなくなります。
突然、白目をむき、口から泡をふいて唇が青くなってビクビクとしだすので、びっくりしますが、たいていは2、3分で治まります(稀に長く続くことがあります)。痙攣は30分以内に止めるべきなので、10分続いていたら救急車です。なお、けいれん中に舌を噛み切ることはないので、口のなかにスプーンや布を入れる必要はありません。窒息するのでやめましょう。痙攣後すぐに意識が回復して落ち着いたなら、普通に受診をしてください。当院では、再発予防として痙攣止めの座薬を使用します。
意識の回復が悪い場合、痙攣を繰り返す場合など、典型的な熱性けいれんの経過と異なる場合は、髄膜炎や脳炎脳症の可能性もあるため、病院での精査が必要になります。
- ・ 6歳以上の痙攣、発熱を伴わない痙攣、何度も繰り返す熱性けいれん、片側性の痙攣などは、てんかんの可能性も考えられますので、脳波、MRIなどの精査をすすめます。
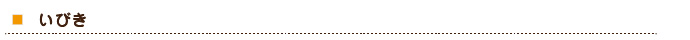
- ・ 「いびきがひどい。寝ている時に息を止めたりして、そのうち呼吸を止めてしまうのではないかと心配で・・」と受診される方がいます。いわゆる睡眠時無呼吸症候群です。小児の睡眠時無呼吸症候群は扁桃肥大(へんとうひだい)、アデノイド肥大に伴う閉塞性(末梢性)の睡眠時無呼吸症候群であることが多いです。この場合は、どんなにいびきがひどくても、呼吸を本当に止めてしまうことはないので、安心してください。ただし、毎晩この状態が続くと、日中の集中力がなくなるなど、日常生活に支障をきたすことがあります。アプノモニターなどで睡眠時無呼吸の程度を評価して、扁桃摘出術、アデノイド切除術を耳鼻科の先生に相談することになります。
- ※ 口蓋扁桃=のどちんこの両脇にあるアーモンド状の塊。口を開けると見えます。小さい人は分かりづらいです。
- ※ アデノイド=咽頭後壁にあります。のどちんこの奥なので、口を開けても見えません。大きくなると鼻腔を後ろから塞ぐことになります。
- ※ 口蓋扁桃もアデノイドも免疫に関与する組織です。5-6歳ごろに最も大きくなります。大きさは個人差があり、また風邪などをひいている時は普段より大きくなったりします。
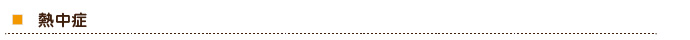
- ・ 高温多湿の環境で、身体が適応できなくなる状態です。熱中症と総称されますが、症状と重症度は様々です。
- ・ 高温環境下では、末梢の血管が開くため、血圧が一時的に下がり、めまい、たちくらみなどの症状がでることが、よくあります。(熱失神:軽症)
- ・ 汗をたくさんかくと、塩分喪失、脱水により、筋肉のこむらがえり症状がでます。(熱けいれん:軽症)
- ・ 塩分喪失、脱水がさらにすすむと、脱力感、嘔吐、頭痛、めまいなどの症状がでます。(熱疲労:中等症)
- ・ さらに悪化すると、循環不全により腎臓、肝臓、中枢神経など全身の臓器に障害がでて、体温調節機構が破綻して40度以上の高熱が持続し、致命的な状態となります。(熱射病:最重症)。
- ・ 熱中症では、塩分を多く含んだ点滴を行います。
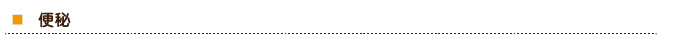
- ・ 乳幼児の慢性便秘は意外と多いです。「毎回コロコロの硬い便がでて肛門から血がでる」「4、5日排便がなくて、おなかをとても痛がる、ご飯も食べなくなる」「頑張ってふんばるのに便がなかなかでなくて、わんわん泣く」などの症状が続く場合はご相談ください。整腸剤、緩下剤を内服したり、定期的に浣腸を行ったりして、排便のサイクルをつくることが大切です。
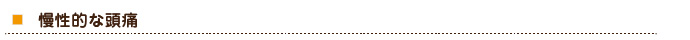
- ・ 間欠的な頭痛を繰り返している場合、小児でも偏頭痛であることが多いです。ストレスや食べ物、体調が悪い時などに症状がでやすくなります。まずは鎮痛薬の内服頓用で様子をみます。ただし、強い頭痛が持続するなど、偏頭痛の経過に合わない場合は精査が必要です。
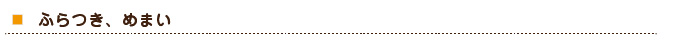
- ・ 症状が続いている場合は、不整脈や貧血などがないか、心電図、血液検査をします。
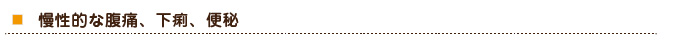
- ・ 過敏性腸症候群という病気があります。ストレスや感染などが契機になって、腹痛や下痢、腹部膨満感を繰り返す状態です。腸の病気というよりは、自律神経系の調節障害と考えられます。「腸は第二の脳」と言われるように、腸は精神状態に敏感に反応する臓器です。
- ・ 意外と多くの人が悩んでいます。(小学生の高学年100人中1~2人、中学生100人中5人くらい、高校生100人中9人くらい)
- ・ 内服薬で、腹痛、下痢などの症状は、かなり良くなる印象ですが、ストレスや悩みが反映される病気ですので、時間がかかることが多いです。悩みは言葉で簡単に説明できるものばかりではないからです。
- ・ なお、過敏性腸症候群の診断に至るためには、まず、炎症性腸疾患などの腸の病気ではないことを確認しなければなりません。
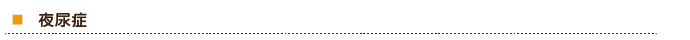
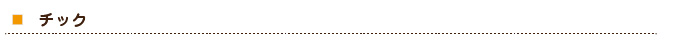
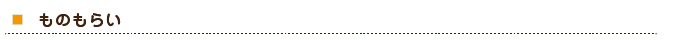
- ・ 関西では「めばちこ」と言います。医学的には「麦粒腫」と言います。まぶたの汗腺や皮脂腺の細菌感染症です。
- ・ 抗生剤の点眼液、(+抗生剤内服)で治療します。
- ・ 手はよくあらい、目をこすらないようにしましょう。
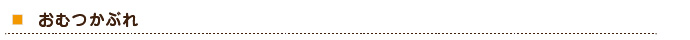
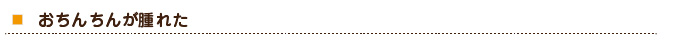
- ・ 亀頭包皮の発赤・腫脹(亀頭包皮炎)は時々みられる病気です。非常に痛々しいですが、抗生剤で治ります。
- ・ 陰嚢の疼痛、腫脹は、精巣茎念転という緊急疾患の可能性があるため、早急に専門医の受診が必要になります。
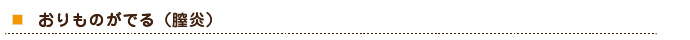
- ・ 小児期は膣内に乳酸桿菌が少なくアルカリ性に傾いているため、自浄作用が弱く、ブドウ球菌や大腸菌などによる感染症が起こりやすいとされます。培養検査を行って、抗生剤で治療します。
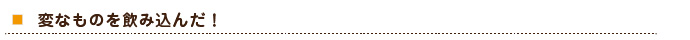
- ・ タバコ、硬貨、ビー玉、鉛筆、おもちゃの釘、液体肥料、磁石、クレヨン、窓に張っているゼリー状のシール、ボタン型電池、犬の糞、洗剤、漂白剤、苛性ソーダ(石鹸作り用に置いていたもの) など・・・・いままでいろいろなものを食べた子に出会ってきました。小さなこどもは何でも口に入れてしまいます。あぶないものはできるだけ遠ざけておく事が大切です。特にコップやペットボトルなどに薬液を入れておく事は要注意です。タバコの吸い殻をジュースの空き缶に入れておくのも危険です。お茶やジュースと間違えて子どもが(大人も!)飲んでしまう事があります。
- ・ 固形物を飲んだ場合の注意点は3点です。
- ① 気道に入っていないか(小さなものだと片方の気管支だけを詰まらせて、当初は呼吸症状が目立たない事があるので注意が必要です。)
- ② 食道狭窄部につかえている場合(胸部に違和感が残るため、取り出すか落とすかの処置が必要になります。)
- ③ 溶けると危ないものか(ボタン電池などが胃にとどまっている時は摘出を試みます。ただし胃を超えた場合は様子をみることになります。)
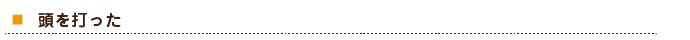
- ・ 非常に多い主訴です。
- ・ 判断するべきは、頭部CTをとるべきかどうか、という点です。つまり、頭蓋内損傷が疑われるかどうかという事です。
- ・小児の頭部外傷に関して、CTの適応を決める論文は何種類かありますが、その中の一つを要約してご紹介します。次のうち、一つでも満たしたものはCT検査をするべきとされます。
| □ |
5分以上の意識消失 |
□ |
5分以上の記憶喪失 |
| □ |
異常な傾眠傾向 |
□ |
頭部打撲後の3回以上の嘔吐 |
| □ |
虐待の疑い |
□ |
頭部打撲後のけいれん |
| □ |
GCS14未満(1歳以上)GCS15未満(1歳未満) |
□ |
頭蓋骨の陥凹 |
| □ |
頭蓋底骨折の疑い |
□ |
神経学的異常 |
| □ |
1歳未満の場合は5cm以上の皮下血腫(たんこぶ)がある場合 |
□ |
時速40キロ以上での交通事故 |
| □ |
3m以上からの転落 |
□ |
発射体や落下物での損傷 |
頭を打ってこられる患者さんで、上記を満たすことは滅多にありません。ただし、3か月未満の乳児であったり、お母さんの印象でいつもと様子が違う、という場合は慎重な判断が必要だと思います。頭を打ったその日は、注意して経過をみてもらうことになります。
思いつくものを羅列しましたが、上記以外でも、お子さんに関して、心配な事、気になっている症状などありましたら、ご相談ください。
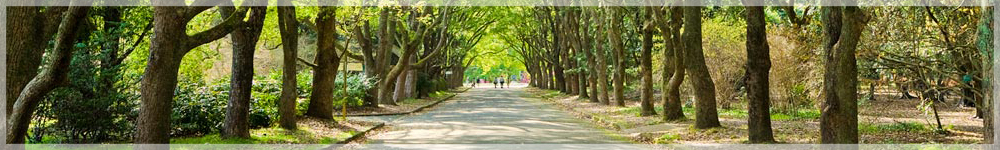

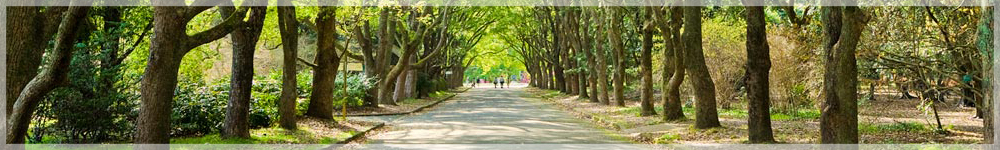
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()